ダウン症候群(ダウン症)とは?その特徴と症状、支援方法について解説します
- その他障害・疾患
- ダウン症
ダウン症候群(21トリソミー)の基本情報
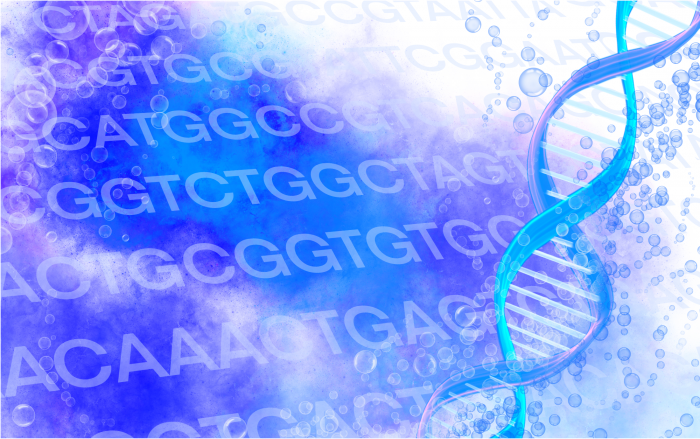
ダウン症候群(ダウン症)は、21番の染色体が通常の2本ではなく3本存在することによって発生する先天性の疾患です。
ダウン症候群の発見と歴史
正式名称は「ダウン症候群(Down Syndrome)」で、イギリスの医師ジョン・ラングドン・ダウン博士によって1866年に初めて報告されました。
その後、1959年にフランスの遺伝学者ジェローム・ルジョンによって、21番染色体のトリソミーが原因であることが発見されました。
発症頻度
ダウン症の発症率は約700人に1人とされており、母親の年齢が高くなるにつれて発症率が上昇することが知られています。
出生前診断や出生後の血液検査によって確定診断が行われます。
ダウン症の種類
ダウン症候群には以下の3つのタイプがあります。
1.標準型(21トリソミー): 約95%のケースで見られ、21番染色体が3本ある。
2.転座型: 約3〜4%のケースで、21番染色体の一部が他の染色体に付着する。
3.モザイク型: 約1~2%のケースで、一部の細胞のみ21トリソミーを持つ。
ダウン症の特徴と症状
顔つき・身体の特徴
ダウン症の子どもには、以下のような身体の特徴が見られることがあります。
●丸くて平坦な顔立ち
●ややつり目が上がっている
●目と目の間が広い
●鼻の穴の幅が広い
●大きめの舌と低緊張の顔の筋肉
●小さめの耳、折れ曲がった耳の形
●皮膚が柔らかく、弾力性がある
●手足が短めで指が太く、手に1本の横線(単一掌横紋)が見られることがある
●筋緊張が低いため、身体が柔らかく関節が長く動きやすい
●足の指の間隔が広く、特に親指と第二指の間が広い傾向がある
●握力が弱く、物をつかむ力が発達しにくい
知的発達の遅れと学習能力
ダウン症の子どもは、一般的に知的発達がゆっくりしています。
その程度には個人差があり、適切な支援を受けることで学校教育を受け、社会に適応することも可能です。
中には大学を卒業している人もいます。
●抽象的な概念の理解が難しいことがある
●短期記憶よりも視覚的な情報やルーチンの学習が得意
●反復学習を通じてスキルを向上させやすい
●集中力が持続しにくいが、興味のある分野には熱心になることが多い
言語発達の特徴
●言葉の理解は定着しやすい傾向があるが、発話が遅れることがある
●視覚的な情報を活用することでコミュニケーション能力を高めることができる
●語彙が限られることがあるが、ジェスチャーや絵カードなどの補助ツールを活用すると効果的
●発音が不明瞭になることがあり、口腔機能のトレーニングが推奨される
運動機能の発達
●ハイハイや歩行の開始が遅くなることがある
●継続的なリハビリや療育によって運動能力を向上させることが可能
●バランス感覚や協調運動が弱いため、転倒しやすい
●指先の動作(微細運動)の発達が遅れ、ボタン掛けや鉛筆の持ち方が難しいことがある
視覚・聴覚の認知処理
●視力や聴力に問題があることが多いため、定期的な眼科や耳鼻科の検査が推奨される
●斜視や遠視、乱視が見られることが多い
●中耳炎を繰り返しやすく、聴力低下を引き起こすことがある
ダウン症と合併症
ダウン症と心疾患
約50%のダウン症児に先天性心疾患が見られ、特に「心房中隔欠損症」や「心室中隔欠損症」が多いとされています。
●心疾患の種類によっては手術が必要となるケースもある
●心臓の機能に影響を及ぼし、疲れやすさや呼吸困難を引き起こす可能性がある
消化器系疾患
●腸閉塞やヒルシュスプリング病のような消化器系の問題が発生することがあります。
●胃食道逆流症(GERD)が見られ、食べたものが逆流しやすい
●便秘が慢性的に続くことが多い
代謝・内分泌系疾患
●甲状腺機能低下症が多く、成長や発達に影響を与える
●肥満になりやすい傾向があり、適切な食事管理が重要
●1型糖尿病のリスクが一般よりも高い
眼系疾患
●白内障が若年期に発症する可能性がある
●斜視や遠視、近視が多く見られる
●眼科の定期検診が推奨される
聴覚障害
●中耳炎を繰り返しやすく、聴力低下につながることがある
●耳鼻科の定期的な検査が推奨される
血液系疾患
●白血病の発症率が一般の子どもよりも高いとされています。
●一部のダウン症児では血小板や赤血球の異常が見られることがある
呼吸器系疾患
●睡眠時無呼吸症候群(SAS)が見られることがあり、睡眠の質に影響を及ぼす
●免疫機能が低いため、肺炎や気管支炎などの感染症にかかりやすい
整形外科的問題
●骨密度が低く、骨折しやすい
●脊椎に異常が見られることがある
●股関節脱臼のリスクが高い
ダウン症の寿命と健康リスク
過去には寿命が短いとされていましたが、現在は医療の進歩により平均寿命は60歳まで延長されています。
ダウン症の診断・検査方法
出生前検査(出生前診断)の種類
●母体血清マーカー検査
●非侵襲性出生前遺伝学的検査(NIPT)
●羊水検査・絨毛検査
エコー検査でわかる特徴
超音波(エコー)検査で首の後ろのむくみが確認されることがありますが、確定診断とはなりません。
ダウン症の子どもへの接し方と支援
日常生活でのサポート方法
●わかりやすい言葉で伝える
●生活リズムを整える
●適度な運動や遊びを取り入れる
●感覚統合療法や作業療法を取り入れ、日常生活スキルを向上させる
●集団生活に適応するための社会性トレーニングを行う
得意なことを伸ばして自信をつける
●個々の得意分野(音楽、絵、スポーツなど)を活かすことで自信を持たせることが大切
●遊びの中で学びを取り入れ、学習意欲を高める
●コミュニケーションの練習をサポートし、自己表現の幅を広げる
スモールステップで成功体験を積む
●小さな目標を達成させることで、学びを高めることができる
●ポジティブなフィードバックを積極的に行い、自己肯定感を高める
●失敗を恐れずにチャレンジする機会を提供する
教育・福祉支援
●特別支援教育の活用(特別支援学級、支援学校など)
●早期療育プログラムの利用(言語療法、理学療法、作業療法など)
●福祉サービス(障害者手帳、医療費助成、就労支援など)の活用
まとめ
ダウン症は21番染色体の異常によって発生する先天性疾患であり、様々な特徴や症状を持っています。
知的発達の遅れが見られるものの、適切な支援と治療によって社会で活躍する人も多くいます。










