アスペルガー症候群とは?症状・特徴・具体的な対応や支援方法
- 発達障害
- ASD(自閉症スペクトラム)
- 障害診断について
- 支援方法・家庭での過ごし方
アスペルガー症候群という言葉を耳にしたことがあるでしょうか?
ASDに含まれる発達障害のひとつです。
このコラムでは、アスペルガー症候群の概要、症状や特徴、具体的な対応や支援方法、成人の場合との違いなどについて解説します。
お子さんがアスペルガー症候群かもと心配されている方、理解を深めたい方、ぜひ参考にしてください。
アスペルガー症候群とは
アスペルガー症候群とは、具体的にどのような障害なのでしょうか?
概要

アスペルガー症候群とは「社会性やコミュニケーションに困難を伴う発達障害の一種」です。
以前は自閉症・アスペルガー症候群・広汎性発達障害など、症状や特徴により様々な名称で呼ばれていました。
現在は「自閉スペクトラム症(以下、ASD)」という名称に統合されています。
ASDは社会的コミュニケーションや対人関係の形成の難しさや、興味・行動・活動の範囲が狭く、こだわりや感覚刺激の過敏さ、または鈍感さがあるなどの症状が早期からみられます。
アスペルガー症候群はASDの一種ですが、「知的発達の遅れなどの知的障害や言語発達の遅れがない」ことが特徴です。
一般的には他のASDのお子さんより学習能力が高く、年齢に応じた言語能力を持っている傾向があります。
具体的には以下の特徴があります。
• 友達とのコミュニケーションが苦手
• 共感力が低い
• 非言語的コミュニケーションが理解しづらい
• 特定のものに強いこだわりを持つ
• ルーティンや習慣を好み、変化を嫌う
• 音や光、匂いなどに過敏
• 触覚に鈍感
• 話す言葉が特徴的
• 表情やジェスチャーが乏しい
アスペルガー症候群の原因
アスペルガー症候群の原因は完全には解明されていませんが、遺伝的要因や脳の構造や機能の違いなどが関係すると考えられています。
遺伝的要因
遺伝的な要素が強く、家族内に同じような特徴を持った人がいるケースが典型的です。
いくつかの研究では特定の遺伝子が発症に関与する可能性が指摘されています。
脳の構造や機能の違い
脳構造や脳機能に特徴があり、脳の言語処理領域の活動が弱かったり、社会的な情報を処理する脳のネットワークの接続が弱いことなどが挙げられます。
その他、環境要因や出産時のトラブルなどが発症に関与する可能性が指摘されています。
アスペルガー症候群の特徴
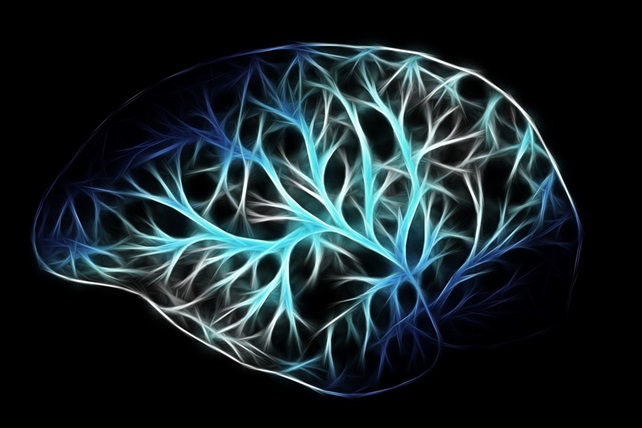
症状の特徴は対人関係の難しさ、強いこだわり、感覚の過敏さ、社会的コミュニケーションの困難さです。
対人関係の難しさ
社会性やコミュニケーションに困難をきたし、中でも対人関係は最も大きな課題のひとつです。
表情や声のトーン、相手の気持ちや表情を読み取ることが難しい特徴があります。
適切なコミュニケーション方法が分かりにくいため、対人関係において孤立しやすい傾向にあります。例えば、
• 相手の顔色が悪いことに気づかず、配慮のない発言をする
• 冗談や皮肉が理解できず、真に受ける
• 自分の興味のあることばかり話し、相手の話に耳を傾けない
• 会話のタイミングが分からず、空気を読めない行動をする
など、様々な問題が生じます。
こうした対人関係の難しさは以下の方法によって改善できます。
• 社会性やコミュニケーションに関するトレーニングを受ける
• 相手の気持ちや表情を読み取る練習をする
• 適切なコミュニケーション方法を学ぶ
• 失敗を恐れず、積極的に人と関わるように心がける
強いこだわり
特定の物事や行動に強くこだわり、変化を嫌い、強い執着を示す傾向があります。
例えば、次のようなこだわりが見られます。
• 特定の物や行動、ルールなどへの強い執着
• 同じ道を毎日歩かないと不安になる
• いつもと同じメニューしか食べられない
• 些細な変化にも強い拒否反応を示す
興味のある分野への集中力や探求心を高めるメリットもある反面、日常生活において問題を引き起こすこともあります。
環境を整え、ルールを明確にする、見通しを持たせるなど、その人の特性に合わせた対応が必要です。
また、こだわりを個性や強みとして活かすなど、個々に合わせた対応と理解が必要です。
感覚の過敏さ
感覚情報の処理が通常の人とは異なるため、感覚過敏に悩まされることがあります。
以下のような特定の音、光、匂い、味、触感などに対し、過度に敏感になる状態です。
• 明るい光や特定の色(例:蛍光灯、ネオンサイン)
• 大きな音や特定の音(例:掃除機の音、赤ちゃんの泣き声)
• 特定の素材(例:ウール、化学繊維)や肌への接触
• 特定の味(例:苦い、酸っぱい)
• 特定の匂い(例:食べ物、香水)
日常生活に支障をきたすことが多く、不安やストレスの原因となるため、感覚過敏への理解と適切な対応が必要です。
対策としては、以下のような方法があります。
• 環境調整: 刺激を少なくし、刺激を軽減するための工夫を行う
• 感覚統合療法: 感覚情報を適切に処理できるようにする療法
• 認知行動療法: 過敏な反応をコントロールするための心理療法
社会的コミュニケーションの困難さ
冗談や比喩を理解しにくく、言葉通りの意味で解釈します。
いわゆる「空気」が読めないために、言葉の理解と解釈、非言語コミュニケーション、会話のキャッチボール、友達関係を築くことが苦手です。
人間関係の構築や維持が難しいため、集団行動になじみにくく、孤立しやすいなどの問題が生じがちです。
行動面の特徴
行動面では、対人関係・こだわり・感覚・コミュニケーションなどに以下のような特徴がみられます。
• 友達作りや人間関係の構築が難しい
• 冗談や比喩を理解しづらい
• 表情や仕草など、感情表現や非言語的なコミュニケーションが苦手
• 共感力が低く、相手の気持ちを考えづらい
• 特定の物事や行動に固執し、変化を嫌う
• 興味のある分野に没頭し、他のことを忘れがちになる
• 音、光、触覚、味覚などの刺激に敏感で、不快に感じる
• 特定の素材の衣服や食べ物を受け付けない
• 騒音や人混みに耐えられない
• 会話を始めるのが苦手
• 話題が続かず、一方的に話し続ける
• 自分の興味のあることばかり話し、相手の興味関心を無視する
子ども特有の症状
アスペルガー症候群は子どもと成人の間で症状にやや違いがあります。
子どもの場合は友人関係を築くのが難しい、言葉の意味を文字通りに捉える、冗談や比喩を理解するのが難しい、感情表現が乏しい、強いこだわりがあり、変化を嫌う、感覚が過敏で、特定の音や匂いに強い反応を示すなど、社会性やコミュニケーションの難しさが目立ちます。
一方、大人になると、社会性やコミュニケーションの難しさが多少改善される傾向があります。それでも依然として人との距離感がつかみにくい、コミュニケーションが一方通行になりがち、空気が読めない、物事の優先順位がつけられない、強いこだわりがある、融通が利かないなど、日常生活や仕事で困難さを感じる場合があります。
対応や支援法
アスペルガー症候群のお子さんへの対応や支援はどのようにすればよいでしょうか?
以下に具体的なポイントを挙げていきます。
環境を整える
環境の変化や刺激に敏感な傾向があるため、落ち着いて生活できるように環境を整えることが先決です。
• 刺激の多いポスターやキャラクターグッズなどは、視界に入らないようにしましょう。部屋はシンプルにまとめ、視覚情報を減らすことが落ち着きにつながります。
• テレビやラジオの音量は控えめにし、必要のない音は消しましょう。また、一定のリズム感のある音楽などを流すことで落ち着きを促せます。
• 規則正しい生活リズムは安心感を与えます。起床時間、食事時間、就寝時間などをできるだけ固定し、生活しやすい環境を整えてあげましょう。
• 落ち着ける場所を確保しましょう。個室やテントなど、自分だけの空間があると安心感を得られます。
これらを意識して環境を整えれば、落ち着いて過ごせる環境を作れます。
わかりやすく具体的に指示する
コミュニケーション能力や感覚の過敏さ、強いこだわりなどを考慮すると、わかりやすく具体的な指示をすることは非常に重要です。
• 指示は短く、簡潔に
• 1度に複数の指示を出さない
• 指示内容を書き出す
• 絵や写真など視覚的なサポートの活用
• 具体的な行動をイメージできるような説明
• 段階的に指示を細分化
• 指示が理解できているか、逐次確認
• ジェスチャーや表情を交えて伝える
これらの方法を組み合わせると、指示を理解し、適切な行動をとれるようになります。
見通しを持たせる
未来予測や状況の変化への対応が難しいので、見通しを持たせることは不安や混乱を軽減し、自信を持って行動させる手助けになります。
• スケジュール表で一日の流れや、これから行う活動について視覚的に示します。自分が何をすべきか、次に何が起こるかを理解しやすくなります。
• 外出や予定変更など、普段と異なることが起こる場合は、事前に予告して心の準備をさせます。いつ、どこへ行き、何をしなければならないのかを予め説明します。
• 選択肢を与え、自分が何をするかを選択したり決定する機会を設けましょう。例えば、着る服や、食べるおやつなどを選択肢から選ばせてあげましょう。
• 複雑な課題はスモールステップに分解して段階的に教えることで、理解しやすくなります。また、各ステップを達成するごとに褒めて自信を育てます。
• 新しいスキルを習得するには反復練習が大切です。得意な活動と苦手な活動のバランスを取りながら、反復練習によってスキルを定着させましょう。
具体的に褒めて自信をつける

得意なことや好きなことに熱中し、こだわりが強い傾向があるため、お子さんの適性を伸ばすために具体的に褒めて自信をつけてあげましょう。
自己肯定感が高まり、学習意欲や行動力にも繋がります。
曖昧な褒め方ではなく、どのような点が優れているのかを伝えるほか、結果だけでなく、努力の過程を認めましょう。
また、自信を損ねないために友だちとの比較は避けましょう。
自信をつけるためのサポートにはSST(ソーシャルスキルトレーニング)も有効です。
SSTはロールプレイングやシミュレーションを通じて、社会生活に必要なコミュニケーションスキルを身につけるためのトレーニングです。
例えば、「あいさつをする」「相手の話を聞く」「自分の意見を伝える」などの基本的なスキルから、「友達との遊び方」「集団行動のルール」「トラブルの解決方法」など、より複雑なスキルまで段階的に練習します。
SSTに取り組むことで相手の気持ちを理解したり、自分の気持ちを適切に表現する能力を高められます。様々な場面での適切な行動を身につけることで、友達との関係を築いたり、集団生活にスムーズに馴染めるようになります。
発達障害のあるすべてのお子さんに有効な支援方法であるSSTを通じて、社会で自立して生活できるようになります。
根本的な治療法は?
アスペルガー症候群には現在のところ、薬物療法のような直接的な治療法はありません。
しかしながら、上述のような様々な支援や療育プログラムを通じて、生活の質の向上が可能です。
高機能自閉症との違い
アスペルガー症候群と高機能自閉症はいずれもASDに含まれる発達障害です(※)。
両者の共通点は、知的発達の遅れがないことや対人関係が困難なこと、活動や興味の範囲が狭いという点です。
両者の違いとしては、以下の点があります。
知能指数
アスペルガー症候群はおよそlQ70以上、高機能自閉症はlQ71以上と分類されます。
言語発達,
アスペルガー症候群は言語発達に問題がない一方で、高機能自閉症は言語発達に遅れがみられます(ただし、時間の経過とともにその差は縮まるという近年の研究もあります)。
特徴がみられる時期
高機能自閉症では3歳以前にそれらの特徴が現れます。
実際には両者の境界は曖昧で、どちらに分類されるか難しい場合があり、また重複する特徴も多いです。
そのため近年では、両者はあまり区別せず扱われることが増えています。
※アメリカ精神医学会発刊の『DSM-5』(『精神疾患の診断・統計マニュアル』第5版)において2022年以降、両者とも「ASD」の診断名に統一されました。
日本の医療機関もこれに倣う一方、行政や教育の場では現在も慣例として「アスペルガー症候群」「高機能自閉症」の名称が使用されています。
まとめ
アスペルガー症候群はASDに含まれる発達障害のひとつですが、知的発達や言語発達の遅れがないことが特徴で、高機能自閉症とはいくつかの点で異なります。
主な特徴である対人関係の難しさ、強いこだわり、感覚の過敏さ、社会的コミュニケーションの困難さに対して適切に対応するためには、環境を整える、わかりやすく具体的な指示をする、見通しを持たせる、具体的に褒めて自信をつける、SSTで経験を積み重ねる、などの方法があります。
症状への理解と適切な対応はお子さんの成長と社会生活に大きな影響を与えます。
支援者や周囲の人々が理解を深め、適切な対応をとることでお子さんの可能性を伸ばしていきましょう。










