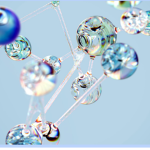「服のタグが気になって着替えたがらない」「大きな音がすると耳をふさいで泣いてしまう」そんな子どもの様子に、不安や戸惑いを感じている保護者の方も多いのではないでしょうか。
こうした感覚に対する強い反応は「感覚過敏」と呼ばれ、発達障害との関連があることも知られています。感覚過敏は個性のひとつでありながら、日常生活に困難を感じる場面もあるため、正しい理解と適切な対応が大切です。
そこで本記事では、感覚過敏の基本的な特徴から発達障害との関係、子どもへの影響、そしてご家庭でできるサポート方法まで解説していきます。
感覚過敏とは?

「感覚過敏」という言葉を耳にしたものの、実際にどのような状態なのかよくわからない…という方も多いでしょう。
感覚過敏とは、光や音、触った感触など、さまざまな感覚に対して人一倍敏感に反応する状態を指します。
まず本項では、感覚過敏の定義や主な症状、似た特性との違いについて解説していきます。
感覚過敏の定義と主な症状
感覚過敏とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚などの五感において、外からの刺激に過敏に反応してしまう状態を指します。主な症状には以下のようなものがあります。
●突然の大きな音に過剰に反応する
●光や照明がまぶしすぎて目を開けられない
●衣服のタグや縫い目が気になって着替えができない
多くの人が気に留めない程度の刺激でも、苦痛や不安、パニックを引き起こす場合があります。特に発達障害(ASD・ADHD)においては、聴覚や視覚、触覚といった複数の感覚に過敏さが見られることが多く、日常生活や学校・園の環境で困難を抱えることもあります。
感覚鈍麻との違いについて
感覚鈍麻は感覚過敏とは逆に、痛みや熱などに敏感に反応せず、刺激を受け取りにくい状態です。刺激が弱すぎるため「感覚探求」として、強い刺激を自ら求める行動(例ぐるぐる回る・大きく手を叩く)につながることがあります。
感覚過敏も鈍麻も、脳の感覚情報処理に偏りがある状態であり、ともに日常生活に支障をきたします。発達障害のある子どもの中には、過敏と鈍麻の両方を併せ持つケースもあります。どちらも「脳の特性」であり、無理に直すのではなく、環境調整や支援によって生活しやすさを整えることが大切です。
感覚過敏がある子どもの行動例
感覚過敏を持つ子どもには、以下のような具体的な行動が見られることがあります。
聴覚過敏:教室のざわつきや掃除機の音で耳をふさぐ、耳栓を望む
視覚過敏:蛍光灯や太陽光がまぶしすぎて目を閉じる、LED画面を避ける
触覚過敏:タグ・縫い目のある服を嫌がり、特定の素材しか着ない
嗅覚過敏:香水や給食の匂いで不快を訴える
味覚過敏:特定の食感・味を拒否し、偏食傾向になる
これらの行動は「我慢が足りない」わけではなく、「苦痛を避けるための自然な反応」です。ご家庭や園・学校での配慮や支援によって、子どもが安心して過ごせる環境づくりがとても大切です。
感覚過敏と発達障害の関係
「感覚過敏があるってことは、発達障害なの?」と心配になる保護者も多いと思います。
実際、感覚過敏は自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの神経発達症と併せて見られることがあります。ですが、それがすぐに「発達障害である」というわけではありません。
ここでは、感覚過敏と発達障害のつながりについて、それぞれの特性と併せて丁寧に解説し、判断の目安や理解のポイントをお伝えしていきます。
自閉スペクトラム症(ASD)との関係
自閉スペクトラム症(ASD)を持つ子どもの約60〜90%に感覚過敏(または鈍麻)などの感覚の問題があると報告されています。特に聴覚や視覚、触覚に過敏さを示すことが多く、たとえば、蛍光灯の光が眩しく感じたり、大きな音で突然驚いたりすることがあります。
感覚過敏はASDの特徴の一つとしてDSM‑5‑TRにも明記されており 、こだわりや常同行動など他のASDの特性と合わせて支援、調整することが重要です。子どもが安心して過ごせる環境を整えるためには、「光が苦手」「音に敏感」という情報を共有し、環境調整や配慮の仕組みを作ることが第一歩になります。
参考元:発達障害ナビポータル
https://hattatsu.go.jp/topics/topics-kankaku-selfcare/?utm_source
ADHDやその他の神経発達症との関係
ADHD(注意欠如・多動症)を持つ子どもでも感覚過敏が見られることがあります。ADHDの感覚過敏では、ASDと同様に音や光に敏感になる傾向があり、選択的注意の難しさや感覚情報の処理の脆さが影響していると考えられています。
また、学習障害や協調運動障害といった、いわゆる神経発達症を併せ持つ場合も、感覚特性への理解が重要です。環境調整や支援計画では、複数の特性を総合的に捉え、感覚の困りごとに対する柔軟な配慮が求められます。
参考元:昭和大学 研究論文
https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-23K06996/23K069962023hokoku/
原因:感覚過敏はなぜ起こるのか?
感覚過敏の根本的な原因は、脳内での感覚情報処理に偏りがあるためだと考えられています。(まだ明確に分かっている段階ではなく、複数の原因が考えられている中の一つ)音や光などの刺激がそのまま過剰に伝わりやすく、脳が適切に「フィルター」をかけられないとされています。
これは先天的な神経系のバランスの差によって生じるもので、ASDやADHDなどの発達障害にも関連があります。他にもストレスや不安、てんかんなどの身体的要因で一時的に過敏になることもあり、原因は多様です。治すことではなく、個々の感覚特性に合わせた環境や支援を整えることで、子どもが安心して過ごせるようになるでしょう。
感覚過敏が子どもの生活に与える影響
感覚過敏のある子どもたちは、日常のなかで思いがけないところで困難を抱えていることがあります。
たとえば、園や学校の集団生活に馴染みにくかったり、ご家庭での些細な音や光にストレスを感じたりすることがありますが、周りからは理解されにくく、自己肯定感や安心感が育ちにくいという悩みも少なくありません。
ここでは、感覚過敏が子どもの生活にどのような影響を及ぼすのかを、具体的な場面ごとにご紹介していきます。
集団生活(保育園・学校)での困難
感覚過敏のある子どもは、教室や保育園という「音・光・人」の刺激が多い環境で大きな負担を感じることがあります。たとえば、急なチャイムや掃除機の音に驚き、耳をふさいだり、蛍光灯の光がまぶしくて目を閉じてしまうといった行動が見られます。
触覚過敏では制服や机・椅子の感触が苦痛になり、集中力が低下し、学習や活動に参加できなくなることもあるでしょう。こうした状態では生活リズムが崩れ、不登校や集団適応の遅れにつながるケースもあります。
ご家庭内でのトラブルやストレス
ご家庭でも、感覚過敏が原因でストレスが生じることがあります。たとえば、洗剤や柔軟剤の香り、食器の音に敏感で、嫌がって泣いたり料理を食べなくなったりすることもあります。また、コロナウィルスが流行していた頃、何度言いきかせても、外出時に子どもがマスクを外してしまい困ったことがあったかもしれません。
感覚的な苦痛は「わがまま」ではなく、子どもなりの苦しさの表現です。ご家庭では無香料製品の利用や、刺激の少ない衣服選び、穏やかな音環境づくりなど、配慮された環境が子どもの安心感を保つ鍵になります。
本人の自己肯定感や不安感への影響
感覚過敏による困難が繰り返されると、「自分は普通じゃないのでは」と自己肯定感を下げる原因になります。一つの刺激で過剰反応し、「また怒られるかも」といった不安からストレスを抱えることもあり、不登校や情緒面の不安が生じることもあるかもしれません。
また、繰り返しの感覚ストレスは疲労感につながり、心も身体も萎縮しがちになります。自己肯定感や安心感を支えるためには、「感じ方に個人差がある」ことを伝えつつ、肯定的な声かけと成功体験の機会を増やすことが効果的です。
感覚過敏への対処法と関わり方
「じゃあ、どうやってサポートすればいいの?」「家庭でできることはある?」と、対応に悩む保護者の方もいらっしゃると思います。
感覚過敏への対応には、子ども一人ひとりに合った環境づくりや接し方の工夫が大切です。また、場合によっては専門的な支援や療育の力を借りることも必要でしょう。
ここでは、感覚過敏のある子どもと向き合う際に心がけたい関わり方や、安心できる環境をつくるための工夫、相談先の活用について解説していきます。
子どもに安心感を与える声かけや接し方
感覚過敏がある子どもには、安心できる言葉が大きな支えになります。以下のような関わり方を意識するとよいでしょう。
共感的な言葉かけ:「びっくりしたね」「光がまぶしかったね」など感覚を受け止める
選択肢を与える:「◯◯使う?それとも◯◯に行く?」と主体的な選択を促す
段階的対応:少しずつ慣れるために、音を小さく流す、短時間使うなど段階的に取り組む
このように声かけを伴う配慮は、「自分の気持ちを大切にされている」と子どもに実感させ、自信や安心感を育てる土台になっていくはずです。
環境調整でできる配慮のポイント
感覚過敏の子どもには、刺激を抑えた「居心地のよい環境づくり」が鍵です。たとえば、下記のようなポイントがあります。
聴覚:防音カーテンやラグで家具音を吸収し、イヤーマフや耳栓で大きな音を緩和
視覚:間接照明や遮光カーテン、調光ランプ、日差し対策の帽子やサングラス
嗅覚・触覚:無香料洗剤やタグのない柔らかい素材の服を選んであげる
これらを組み合わせることで、ご家庭や教室でのストレスが軽減されます。無理に慣れさせようとせず、「苦手な感覚を避ける」ことが子どもの安心につながる重要な支援です
感覚統合療法や専門的なアプローチ
感覚統合療法(SI)や専門的支援は、感覚過敏への効果的なアプローチです。主に以下が挙げられます。
感覚統合療法
作業療法士等が遊びや運動を通じて体感覚・前庭覚を刺激し、子どもが心地よく刺激を処理できるよう支援
認知行動的アプローチ
不快な音などに段階的に慣れる脱感作技法を専門家が導入
環境調整コンサル
専門家がご家庭や学校を訪問し、気になる刺激への配慮と関係者へのアドバイスを行います
ご家庭でも感覚統合に基づいた遊びが取り入れやすく、継続することで効果が期待できます。専門的な支援と日常の工夫を組み合わせて、子どもの安心できる生活をサポートしましょう。
受診や相談が必要なケースとは?
感覚過敏に気づいたけれど、「でも、誰に相談すればいいの?」と不安を抱える保護者もいらっしゃるかもしれません。その中でも特に次のような場合は、早めの受診や相談がおすすめです。
3ヶ月以上、日常生活で支障が続いている
感覚過敏が継続し、ご家庭や園・学校で過剰なストレスや回避行動が見られる場合、小児科学会のガイドラインでも相談を推奨しています。
家族の工夫だけでは改善が見られない
無香料洗剤を使っても香りを嫌がる、音を遮音しても耳をふさぐなど、環境調整が有効に働いていないと感じる時。
学びや社会参加に制限が出ている
学校で授業に参加できない、公共の場で不安が強くなるなど、社会的な場面で苦しさが現れる場合。
不安や自己肯定感の低下が見られる
感覚過敏によって、不安感や自己肯定感の低さが続くことで、二次的な情緒問題へつながることもあります。
4歳以降も強く続き、適応困難な場合
幼児期を過ぎても感覚過敏が強く、生活に支障を及ぼしているときは、早めの発達外来相談が望ましいとされています。
まずは、保健センターなどに相談し、必要に応じて専門医、小児科発達外来、作業療法士などへの連携につなげるのが安心です。健康な成長のために、一人で抱え込まず、信頼できる支援に頼る第一歩をぜひ踏み出してください。
まとめ
感覚過敏とは、視覚・聴覚・触覚・嗅覚・味覚などの五感において過敏に反応する特性で、子どもによっては日常生活の中で大きなストレスとなることがあります。
自閉スペクトラム症(ASD)や注意欠如・多動症(ADHD)などの発達障害と関連するケースもあり、個々の感覚特性を理解しながら、丁寧に観察、対応することが大切です。
学校やご家庭での困りごとには、環境調整や安心できる声かけ、感覚統合療法などが有効です。また、生活に支障がある場合には早めに専門機関への相談を検討しましょう。
感覚過敏は「わがまま」ではなく、子どもなりの感覚的な困難の現れです。子どもが安心して過ごせる環境づくりと、周囲のあたたかい理解と支援が何よりのサポートになります。
参考元
発達障害ナビポータル
https://hattatsu.go.jp/topics/topics-kankaku-selfcare/?utm_source
昭和大学 研究論文
https://kaken.nii.ac.jp/ja/report/KAKENHI-PROJECT-23K06996/23K069962023hokoku/
各 支援機関 等