癇癪は乳幼児期から小学生にかけて多くのお子さんに見られる行動です。
乳幼児期ならまだしも、小学生になっても激しい癇癪を日常的に起こす場合、周囲の悩みは深刻です。
家での癇癪にどのように対応すればよいか、悩んでいる保護者の方ももおられることでしょう。
このコラムでは、小学生の癇癪の特徴や原因、発達障害との関係について解説します。
さらに、具体的な対応や相談先についてもご紹介します。
癇癪とは?

癇癪とは「感情のコントロールがうまくできず、怒りや不満を爆発的に表現する行動」のことです。
乳幼児期に多く、成長とともに落ち着いていくケースがほとんどですが、小学生になっても続くことがあります。
また、発達障害の可能性も考えられます。
年齢によって特徴が異なり、乳幼児期は言葉がまだ十分に発達しておらず、泣き叫んだり、体をよじったりするといった身体的な表現が主です。
一方、小学生になると言葉による表現が増え、怒鳴ったり、暴言を吐いたり、物を壊したりする行動がみられるようになります。家での癇癪が続くと、保護者も対応に困ることでしょう。
以下では、時期による特徴とその違いを詳しくみていきましょう。
• 理由なく突然起こる
• 短時間(数分から数時間)続く
• 泣き叫び、転げ回るなどの激しい行動がみられる
• 親の言うことを聞かない
• 周りの人の注意を引こうとする
言葉が未発達で感情のコントロールが難しく、泣き叫んだり、暴れたり、物を投げたり、これらの行動の組み合わせがみられます。
乳幼児期の癇癪は非常に起こりやすく、家や外出先でお子さんが度々癇癪を起こすのを見ると、対処に困るかもしれません。
ですがほとんどの場合、成長に伴って自然に落ち着いていきます。
空腹、疲労、退屈、欲求不満などのさまざまな要因によって引き起こされますが、発達障害や情緒障害が原因の場合もあります。
心配な場合、早めに保健センターや子育て支援機関や医療機関などに相談するとよいでしょう。
小学生の癇癪に関する特徴
乳幼児期に比べて複雑化し、様々な要因が絡み合って起こります。
さまざまな原因があり、それぞれ以下の特徴がみられます。
• 感情のコントロールが難しい
思考力や言語能力の発達に伴い、自分の思い通りにならない状況にうまく対処できないことや気持ちをうまく表現できないことが原因で起こる
• こだわりが強い
自分の興味や関心、こだわりが強く、自分のルールや習慣が崩されることに対して敏感に反応することが原因
• 社会性への適応が難しい
学校生活や友達との関わりの中で、集団生活のルールやマナーを守ることが求められるようになり、うまく対応できないことが原因
• ストレスを抱えている
塾や習い事などをする小学生が増え、学校以外に様々なストレスを抱えています。ストレスが溜まると、些細なことが原因になります。
また、発達障害を持つお子さんは、感情のコントロールが苦手でこだわりが強い傾向があるため、癇癪を起こしやすくなります。
小学生になっても癇癪を起こす頻度や程度がひどい場合は、発達の専門機関や医療機関に相談しましょう。
癇癪の原因とは?
癇癪を起こす原因は身体的、心理的、環境的な要因が複雑に絡み合っています。
・身体的要因…睡眠不足や空腹、疲労、発熱や病気など
・心理的要因…ストレスや不安、怒り、欲求不満など
・環境的要因…しつけや家庭環境、学校環境、友達関係などの人間関係など
これらの要因は単独もしくは複合的に作用します。
原因の特定は難しいですが、これらの要因に注意することで適切な予防や対処が可能になります。
発達障害との関係性
小学生になると自我が芽生え、葛藤を抱えやすくなります。
そのため、一時的に癇癪を起こすことは珍しくありません。
癇癪が頻繁に起こる場合や、年齢の割に強く激しい場合は発達障害の可能性もあります。
たとえば、発達障害の一つであるADHDは衝動性や感情のコントロールが苦手という特徴があります。
発達障害が疑われる時は、発達障害の特性を理解した関わりや対応が必要です。
小学生の癇癪に対して適切な対応
癇癪はお子さんにとって成長過程の一部であり、大人の適切な対応によってコントロールをすることも可能です。
では、具体的にどのような対応をすればよいのでしょうか?
まずは、お子さんをよく観察することが大切です。
癇癪を起こすときは「泣きわめく」「物を投げる」などの表面的な行動が目につき、一見「困った行動」に映るかもしれません。
しかし、根っこには要因となる出来事などの原因があり、お子さん自身が対応できず困っているため、癇癪という行動表現に結びついているのです。
癇癪が起こりやすい状況を把握し、気持ちを切り替える方法を以下で解説します。
癇癪が起こりやすい状況の把握
適切に対応するには癇癪の原因や、お子さんの状況や気持ちを理解していく姿勢が大切です。
癇癪は様々な状況で起こり、またお子さんによっても異なるからです。
どのような場面でお子さんが癇癪を起こしやすいのか?
起こった時の状況を正確に把握することで、事前の対策が立てられます。
また、お子さんの癇癪に対し、その時にとった対応も合わせて記録しましょう。
お子さんに合った対応を見つけ、癇癪の頻度を減らせます。
気持ちを切り替える方法を見つける
癇癪は本人も周囲の人も辛いものです。
未然に防ぐには、気持ちを切り替えることが大事です。
具体的な方法には、以下のようなものがあります。

・深呼吸
気持ちを落ち着かせるのに効果的です。イライラする気持ちを感じたら、ゆっくりと鼻から息を吸い、口から息を吐くことを繰り返しましょう。
・好きなことをする
好きなことは気分転換になり、イライラする気持ちが収まります。音楽を聴いたり、絵を描いたり、本を読んだり、スポーツをしたりなど、お子さんに合うものを見つけましょう。
・その場から離れる
イライラする気持ちを感じたら、一人になる場所に行くなど、その場から離れましょう。
気持ちを落ち着かせ、気持ちを切り替えられます。
お子さんによって、ストレスや癇癪の原因はさまざまなので、個々に合わせて気持ちを切り替えられる方法を見つけましょう。
癇癪が起きたときは
癇癪が起こりやすい状況をできるだけ避けても、防ぎきれず、癇癪が起こることもあります。
そのような場合、どうすればよいのでしょうか?
安全の確保
癇癪を起こしたお子さんは興奮状態にあり、自分自身や周囲の人を傷つける可能性があります。
まずは安全を確保することが最優先です。安全な場所に移動しましょう。
落ち着くまで待つ
癇癪が起きたときは、冷静な対処が大切です。
安全が確保できたら、しばらく様子をみましょう。
本人でもコントロールできない状態ですが、時間が経てば自然に収まることが多いものです。
注意したいのは怒鳴ったり、叩いたりする行為です。
お子さんの心を傷つけ、信頼関係を損なう可能性があります。
気持ちが落ち着くまで静かに見守り、できるだけ冷静に接しましょう。
気持ちを代弁・共感する
お子さんはイライラした気持ちや怒りでいっぱいになっています。
そのような場合、お子さんの気持ちを代弁したり、共感してあげることが大切です。
例えば、「〇〇にイライラしてるんだね」「怒ってるのわかるよ」などと言葉にしてあげましょう。
お子さんの目を見て話を聞くことも重要です。
癇癪後の対応策
癇癪を起こした後は、ただ叱るだけでは逆効果です。
落ち着きを取り戻すまで待ち、癇癪を起こした原因について一緒に振り返ってみましょう。
原因がわかれば、二度と同じ状況にならないように対策をしっかり立てましょう。
また、癇癪を起こしたときにどうすればいいのか、話し合うことも大切です。
落ち着いたことを褒める
お子さんが落ち着いたら、そのこと自体を褒めてあげましょう。
「落ち着いたね」「今はもう大丈夫だね」など、その状態を認めてあげることが大切です。
イライラの原因を共に振り返る
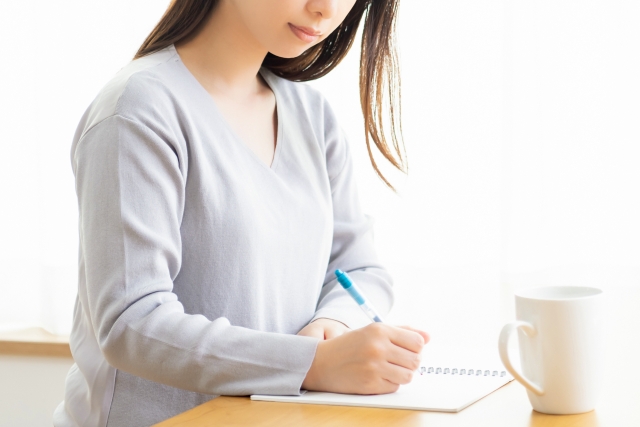
なぜ癇癪を起こしてしまったのか、一緒に振り返ってみましょう。
自分自身の気持ちをうまく表現できない場合は、大人がサポートすべきです。
お子さんの気持ちを代弁し、共感することで、なぜ癇癪を起こしたのかを探りましょう。
例えば、以下のような質問を投げかけてみましょう。
• どんな時にイライラした?
• どうしてイライラしたの?
• どんなことがしたかったの?
• どうしたらよかったと思う?
最初は上手く答えられないかもしれませんが、お子さんの気持ちに寄り添い、繰り返すことで、お子さん自身も自分の気持ちに少しずつ気づけるようになります。
また、原因を振り返ると同じような状況を避けるヒントが得られます。
例えば、宿題をする際にイライラする場合、解き方がわからない、量が多い、遊ぶ予定があるなど、特定した原因によって対応の仕方も変わります。
お子さんと一緒に原因を振り返って気持ちを理解し、癇癪の予防策を立てましょう。
小学生の癇癪に関する相談先

癇癪に関する相談先は学校、医療機関、お子さん家庭センター、児童相談所、発達障害支援センターなど多岐にわたります。
学校ではスクールカウンセラーや養護教諭が相談相手となり、医療機関では小児科や精神科を受診できます。
お子さん家庭センターや児童相談所は、家庭環境やお子さんの発達状況を把握した上で適切な支援を提供しています。
発達障害支援センターでは、発達検査や療育相談など、お子さんの発達に合わせた支援を受けられます。
癇癪への対応に困ったら、一人で悩まずに専門機関に相談してみましょう。
スクールカウンセラーや養護教諭
スクールカウンセラーはお子さんの心のケアや相談にのることが専門です。
癇癪の原因がストレスや不安、人間関係などの問題にある場合、カウンセリングを通してお子さんの心のケアを行い、改善を図ります。
また、保護者の方へのアドバイスや家庭での対応方法についても指導してくれます。
養護教諭は健康管理だけでなく、心のケアにも対応しています。
身体的な原因によるものではないか、生活リズムや食生活に問題がないかなどをチェックし、必要に応じて適切な対応をアドバイスしてくれます。
スクールカウンセラーや養護教諭への相談は、予約が必要な場合があります。
学校のホームページや連絡先を確認し、事前に予約してから相談しましょう。
医療機関
癇癪を繰り返す場合、発達障害の可能性があるかもしれません。
発達障害は「生まれつき脳の働き方に特徴があり、コミュニケーションや社会性、学習などに困難が生じる障害」です。
苦手なコミュニケーションや社会性、情緒面の育ちにくさから癇癪につながることもあります。
医療機関を受診することで発達障害の有無を診断し、適切な治療や指導を受けられます。
専門医はお子さんの様子や発達歴などを詳しく問診し、必要に応じて検査を行います。
検査の結果、発達障害と診断された場合は、療育や投薬治療など、個々のお子さんに合わせた治療計画を立てていきます。
・小児科や精神科: 発達障害の診断や治療
・発達障害専門外来: 発達障害の専門医がいる医療機関では、より専門的な診断や治療
早期に診断と治療を開始することで、お子さんの成長をサポートできます。
子ども家庭センターや児童相談所
発達や子育てに関する相談は児童相談所や、令和6年4月より各自治体に設置された子ども家庭センターで行われています。
子ども家庭センターは保護者の方やお子さんが利用できる様々な社会資源につなぐ役割も担い、地域の関係機関と連携しながら、子育て家庭を支援しています。
医療機関や専門機関などの情報提供も行っているため、どこに相談してよいかわからないときは相談してみましょう。
発達障害支援センター
発達障害支援センターは発達障害に関する相談や支援を行う専門機関です。
癇癪の原因が発達障害によるものかどうか、不安がある場合は相談するとよいでしょう。
発達障害支援センターでは以下の支援が受けられます。
• 専門医による診察
• 心理検査の実施
• 療育プログラムの提供
• 親への支援や指導
各都道府県に設置されており、近くの支援センターの情報は、各都道府県のホームページや厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
相談の際には、事前に以下の情報を整理しておくとスムーズです。
• 年齢
• 癇癪の症状
• 癇癪が起こる場面や時間帯
• 発達状況
• 家族歴
相談員は専門的な知識と経験を持っているため、癇癪の原因や適切な支援方法について親身になってくれます。
発達障害の可能性が不安な場合、まずは相談してみましょう。
小学生の癇癪に適切な対処とサポートまとめ
小学生のお子さんの癇癪は乳幼児期と比べて表現方法が変化するため、保護者は戸惑うかもしれません。
適切に対処するには、背景に様々な要因があることや、発達障害が隠れている可能性についてまず理解を深めましょう。
癇癪の原因やお子さんの気持ちを正しく理解することが大切です。
そのうえで適切な対処をとれば、お子さん自身が少しずつ癇癪をコントロールできるようになります。
癇癪が頻繁に起こる場合や、日常生活に支障をきたすような場合、ひとりで悩まず専門機関に相談してサポートを受けることをお勧めします。
焦らずにお子さんと向き合っていきましょう。
ステラ個別支援塾では無料体験実施中
ステラ個別支援塾は発達障害のお子さま向けの個別指導塾です。
個々のお子さまに合わせたオーダーメイドの授業でお子さまの成長をサポートします。














